~目次~
現在地の確認
ある目的地に向かいたいのであれば、“現在地”を知ることが大切!
道に迷ったとき、あなたが見失ったのは目的地ではなく現在地です。
地図を見て確認するのも、目的地の前に現在地ですよね?
自分が今どこにいるかを知る
これがとても重要です。
自分がどこにいるのか分からないまま目的地に向かうことはできません。
何かを習得しようとするとき
目的を達成しようとするとき
今の自分にあるもの(できること)とないもの(できないこと)がなんなのか。また、足りないものをどう補っていくのか。新たに必要なものは何かを見極めます。
そうすることで、不安は軽減され、着実に一歩ずつ歩みを進めることができます。

~デッサンする~では、洋楽(英語の歌)を練習するのに必要な最低限の知識を得て、まずは聞き取りを中心に“なぜ英語が聞き取れないのか”を分析しました。
- 英語の発音には腹式呼吸が必要
- 日本語の音節、リズムでは英語にはならない
- 日本語にない音が英語にあり、また英語にない音が日本語にはある
- 英語は”音そのもの”を伝える言語
このようなことから、わたしたち日本人には聞き取れない音があり、また発音しても通じない音があることを確認しました。
次に~デザインする~では、聞き取った音を再現(発音)する練習を中心に、“なぜ英語らしい発音にならないのか”を分析しました。
- 英語は子音骨格(子音中心の音声認識)
- 音節を間違うとリズムや音程も間違ってしまう
- 英語に長音や促音は存在しない
- 呼吸の連続性に伴って音が変化(リンキング)する
このようなことから、せっかくアルファベットで英語の音素を練習しても、歌の中で上手く発音できなかった理由が見つかりました。
さて、ここまでのことが十分理解できていますか?
知識としての理解だけでなく実践での成果も確認してください。
- 腹式呼吸が不十分で、語末の引き延ばしが上手くできない
- まだ必要のないところでうっかり母音を入れてしまう
- 発音できない子音の音素がある
- 音節も頭ではわかっているけど、発音では等間隔になってしまう
- 音の連結には慣れたけど、同化がよくわからない …など
確実に目的地に近づくために、今来た道を何度も往復したり、どこかのチェックポイントまで戻って別のルートを探したりすることが必要です。
同じ道を何度通っても、それは決して無駄ではありません。
一度目には気づけなかったことに気付くことができます。
同じ景色がまた違って見えることがあります。
今あなたがいる地点はどこですか?
それさえ知っていれば迷うことはありません。
客観的に自分を観察する
自分自身を客観的に見るのは難しいことです。
他人のことにはよく気が付くのに、自分のこととなるとさっぱり…という人も。
とくに歌に関しては、“自分なりにはやっている”という自負があればあるほど客観的に自分の歌を聞くことができなくなります。
ボーカルレッスンでも、“客観的視点をもつ”ということを早い段階から訓練します。
いくら指摘されても、本人が自覚できないことは改善できないからです。
すぐに改善できなくても、“ここが変だ”とか“もっとこうしたい”と思えるのなら僅かずつでも前進できます。
他者からの指摘を受けられないのなら、なおさら自分を客観的に捉える力を身に付けなくてはなりません。
動画を撮る

簡単な方法として、定期的に自分の歌唱動画を撮ってみましょう。
歌っているものだけなく、アルファベットの発音や英文を読んでいる自分を撮影することもお勧めします。
今はスマホがありますから、誰でも手軽にどこででも録画が可能です。
―録音じゃだめ?
今は録画にしてください。
英語は”音を見せる”ことも大事でしたよね。
口元の動きがしっかり見える(見せる)ように撮影しましょう。
動画を撮る際は、この動画を見るであろう数分後の未来の自分にメッセージを送るつもり行います。
カッコ良く歌うことが目的ではないので、“どこを練習しているのか”が分かるものにしてください。
未来の自分に「ここを聞いて(見て)!」というつもりで。
もっと後に動画を見返したとき、「この頃はとくに〇〇を練習していたな」と分かるくらいのものが良いです。定期的に記録していれば成果の確認にも役立ちます。
目的をもって動画を撮ったら、さっそく一視聴者の目と耳で観察しましょう。
自分が“見せたいもの”がちゃんと表れているか。
逆に意図せず“見せてしまったもの”は何かを明らかにします。
- ◎ 声になる前に口のかたちがつくれるようになった
- ◎ 以前より呼吸のつながりが感じられ音のつながりも良くなった
- ◎ 苦手なあの音がしっかり鳴っていた
- ✖ 不自然な口の動きが多くある
- ✖ 思ったよりもアクセントがついていない
- ✖ 全体的に速く歌っていてテンポがはしっている …など
できるだけ具体的にことばにしてください。
検証するポイントを事前に項目化しておくと良いでしょう。
“やっているつもり”でも外に現れていなければ“やっていない”と判断します。
最初からプロのようにさらっと上手く歌えるわけがありません。
自分が想像する以上に大げさにやらないと他者には伝わりません。
まずは自分自身に伝えるつもりで“見せる”歌い方をしましょう。
リスニングを強化する

英語の歌を歌おうと思ったら、“とにかく浴びるように聴く”からスタートしたと思います。それは洋楽初挑戦の人であればなおさらでしょう。
―ただいっぱい聴いていたら歌えるようになる?
そんなことはないですよね。
もしそうなら、普段から洋楽を聴いている人はすぐに歌えるということになります。
聴き方が違うのです。
普段英語の歌を聴いている人は、英語を聞いているのではなく音楽を聴いています。まぁ当たり前ですよね(^^;
ですが、今回『英語歌唱メソッド』を実践するため、“英語で歌う”ために洋楽を聞いた人は、英語を聞いていたと思います。
もっと言えば、“音”を聞いていたし、“呼吸”を聞いていたのだと思います。
そうでなければ、何度聞いても1フレーズ歌い出すことも無理だったのでは?
もっと音が聞こえるようになるため、もっと呼吸を感じ取れるようになるために英語の特性を知り、必要に応じて知識を導入し補完してきました。
聞こえなかったせいで鳴らせなかった音
鳴らせなかったことで聞こえなかった音
それらが、“音”に集中したことや知識の助けによって徐々に改善しています。
もちろんまだ聞き取れない音も上手く発音できない音もあります。
それでも、音楽として聞き流している状態に比べたら着実にリスニング力(聴く力)は向上しています。
得意な音や不得意な音も自覚があるでしょう。
―それじゃあ、歌の練習はしていないってこと?
確かにまだ歌の練習をしている実感は湧かないかもしれませんね。
でも『英語歌唱メソッド』は
歌うために必要な知識と技術を「英語で歌う」ことで手に入れる!
ですよね。
英語で歌うこと=歌が上手くなる練習
必死に英語を聞き取ろうと浴びるように聴いている間だって、いつも以上に音楽を味わっています。
日本語の歌なら、音程を覚えてしまったら後は簡単。
母語ですから歌詞を暗記するか見るかしながら歌えば一応は歌えてしまいます。(上手い下手は別として)
せいぜい外してしまった音程を修正するくらいです。
最初からデッサン自体が適当なのです。
浴びるように聞いたとしても、細部にわたって観察していることはありません。
聴き手として音楽を楽しんではいても、歌い手としてあらゆる情報をつかみ取ろうとはしていません。
“表現する者”として、その楽曲たらしめる個性を読み取るには、かなりの経験則と音楽的知識や才能が必要です。
それではほんの一部の人にしか“上手くなる練習”はできないことになります。
つかみどころのない“歌の上手さ”より、“英語の発音”を上手くする方が分かりやすく、努力しやすいと思いませんか?
一つの音を聞き取ることもできず、思った音も鳴らせない。
そんな人がいくら歌を練習していても上手くはなりません。せいぜい“歌い慣れる”だけです。
直接的に音を聴く力と音楽を味わう力の両方があって音楽を楽しむ力になります。
そこに、音を生み出す力が加わって、音楽(歌)で楽しませられるようになります。
そんな本質的な能力も、不慣れな英語を聞き取ったり発音したりする練習の中で磨かれているのです。
~スポンサーリンク~

歌詞を見ながらリスニング
ここまで、次のような流れで練習してきたと思います。
- 浴びるように聞く(デッサン)
- 聞こえた音と聞こえなかった音の確認
- 知識の導入
- 音の再現(デザイン)
- 歌声の再現(トレース)
1.で、意識的に“英語”を聴きました。
この間にアルファベットなどで英語の音素を練習しました。
2.で、音の聴こえ方に差があることを確認しました。
“かな”に聞こえてしまう音やまったく聞えない音もあったでしょう。
3.では、2.を補完するために英語の知識を導入し、聞こえない理由を探りました。
4.は、3.までの練習で聞き取れた音を中心に、自分で発音できるように練習。
再びアルファベットでの音素確認、また新たな知識を投入し“英語らしい音”に近づけようとしました。
5.では、いよいよ歌の中での“英語らしさ”に挑戦。原曲者と同じように呼吸の連続性を保ちながら、細かに変化するのはかなり難しかったと思います。
ここで一旦歌うのをお休みして、歌詞を見ながら再び“リスニング”に集中してください。
自分が声にしたことで、音の聴こえ方が変わってしまった箇所があると思います。聞いたときには辛うじて予期できたリズム、各音素の個性、リンキングなどが、自分が発音した音のせいで消えつつあります。
自分の声や音を想像せずに、もう一度あるがままの音を観察しましょう。
間違って写し取ってしまった箇所の修正を行います。
これをうちでは“トレースの修正”または“予期の修正”と呼びます。
聞き取れない音は発音できない、と同様に
想像できない音は生成できない
という特徴があります。
間違った想像や予期をしながら、正しい音や声は出せません。
「この子音はもっと鋭かったのか」
「この音はかなりあいまいな音でよかったのか」
「このフレーズの緩急が消えてしまっていたな」
自分ができるかできないかは二の次です。
聞き取ることのできる音も感じ取ることのできる表情も限られています。
つかみ取れたものは放さないでください!
自分の歌や発音のせいで。。。
と、がっかりすることはないですからね。
自分で声にしてみたからこその発見もたくさんありますよ。
瞬時には、連続では、まだ難しかっただけのこと。
一所懸命に練習した音は、以前よりも鮮明に聞き取れると思います。
たとえ英語が上手くなってスラスラと歌えるようになっても、リスニングを疎かにはしないでください。
上手くなればなるほど、つかみ取れる情報は多くなっていくのですから!
あとがき
わたしは20歳から歌の先生をしていますから、他人から歌について指摘を受けることはほとんどなく、自分で自分を指導するしかありませんでした。
でもそのおかげで、自分のことも生徒の一人として捉え、客観的に見つめることができたように思います。
洋楽も10代から歌っていましたから、英語に抵抗はありませんでした。
でも英語が話せるわけでも得意でもありません。
今思えば相当いいかげんな発音で誤魔化していたなと自覚があります。
「たかが発音…どうせ日本人には分からないだろう」
そんな気持ちも正直あったと思います(若気の至りです)。
今も英語が上手いとは思っていませんが、“ちゃんと英語で歌う”ようになってから体や声のコントロールが格段に上手くなったと感じます。
音域も広がり、声の響きも増しています。何より音楽の味わいが深まり、楽しめる音楽の幅が広がり続けています。
おかげでいまだ伸び盛りです( *´艸`)
自分を完全に客観視できる人はそういません。
自分の歌が上手いのか下手なのか分からなくても無理ありません。
だからこそ、はっきりと「聞えた!」「分かった!」「できた!」が必要です。
「聞えない」「分からない」「できない」があっても、それが“何か”が分かればいくらでも対象のしようがあります。練習ができます。
何が分からないのかが分からなくなると人は動けなくなります。
自分がどこにいて、どこに向かっているか…
進むべき方向すら見失ってしまい、諦めてしまうのです。
目的地がどれほど果てしなく遠い場所であっても、自分がどこに向かっているかを知っていれば前進できます。確かな一歩を実感できます。
それはとても楽しい旅です。
自分が進めてきた歩みが消えることはありません。
あなたが、今日もまた新しい一歩を踏み出し、地図を広げ続けていくことを陰ながら応援しています。
>>>次に進む

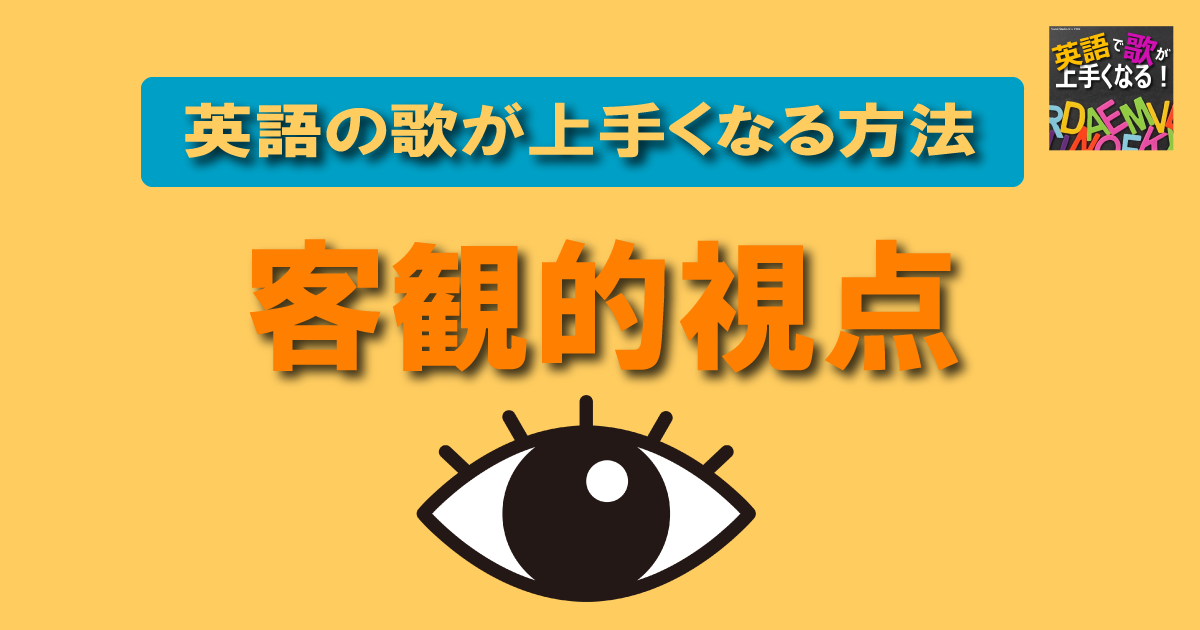
No responses yet