~目次~
無駄な隙間を埋める
呼吸の連続性が保たれていないと英語は上手く発音できないことは再三お話ししてきました。
歌もまたメロディーやリズムのまとまりがあるので、英語の発音と同じように呼吸は長くつながっています。
呼吸については〈英語の発音は腹式呼吸〉や〈呼吸のつながりとリンキング〉などを参照してください。
日本語を話すときの一呼吸は弱くて短いので、少しくらい大きな声を出したところで“呼吸の連続性”を感じることはあまりないと思います。
でも、英語は話すときから一呼吸が強くて長いので、歌にする前から呼吸のつながりを感じやすく、また練習することも可能です。
音程をつけてしまうと“歌うこと”を意識してしまう人は、適当な英語の長文(ニュース記事など)を用意して、それを読む練習を繰り返しましょう。
長文を読む練習をする際は、次のことを確認してから行います。

- 読めない単語の発音をチェックする
- 音節を間違えていそうな単語があればチェックする
- 一呼吸で発音するセンテンス(まとまり)をチェックする
- 内容語(とくに大事な単語)をチェックする
基本は歌と同じです。
とくに意味を知る必要はないですが、どんな内容かを知っていたほうが分かりやすいと思う人は簡単に和訳しておきましょう。
最後の単語からつなぐ
長いセンテンスを一気に読もうとせず、いくつかのまとまりに分け練習してから、最後に全体の流れ(緩急)を理解して発話します。
英語が堪能でない人が文章をいきなり読めば、どんな感じかは分かりますよね。
単語ごと区切るか、ずっと一本調子になるか。
どこまでが一呼吸かもわからないで読み始めても発音が悪くなるだけです。
A man who reads well is a man who thinks well,because they have a background for opinions and for judgment.
(よく読書をする人は良く考える人である。なぜなら彼らの意見や判断には予備知識があるからだ。)
頭の単語から順々に読んでいこうとしない。
リズムがつかめないときは後ろからつないでいきましょう。
well
thinks well
who thinks well
a man who thinks well
…
単語を加えていくときに、内容語と機能語を参考に大事な語を優先しながら組み立てていきます。
内容語と機能語については〈英語で上手く歌うためには緩急が大事〉でおさらいしてください。
“thinks well”では、“well”だけを発音した時より“thinks”のほうが優先され“well”は少し弱くなる…という感じで、緩急をつけながら文を長くしていきます。
“呼吸を途切れさせない”と“英語のリズム”が一度に練習できます。

単語が増え少しずつセンテンスが長くなっていきますから、それに合わせて呼吸も引き伸ばしていきます。
後ろからつなげていくことで、呼吸の連続性は保たれやすくなります。
流暢に“英語らしく”発音したいものですが、”流暢さ=はやい”ではありません。
長い文章にはゆっくり発音するところも、一呼吸置くところもあります。
とても短く発音された機能語の後は大抵長く発音する内容語がきます。
すぐにつっかえてしまうのは“先の流れ”が読めていないからです。いくつかの単語のまとまりを練習してから、それをつなげてください。
母音を拍の頭に合わせる
長めの文章を途切れさせずに読めるようになったら、次は歌の中でも同じことができるように練習します。
ここで忘れてはならないのが
音程はアクセントのつく母音にある
ということです。〈英語の音節を理解する〉でも記しました。
声帯振動があれば音程らしきものが現れます。でも、正確な音程はアクセントのついた母音だけです。
有声子音やあいまい母音にまではっきり音程をつけてはメロディーが変わってしまいます。
だからといって
アクセントのつかない機能語に音程がないわけではありません。
どっちやねんΣ(・ω・ノ)ノ!
と突っ込みたくなるでしょうが、ここが重要です。
呼吸が途切れないことで自然に音程は現れている
日本語は、母音または子音+母音の“かな一文字”が1音節でしたね。
そして、どの音節も基本的には均等に対等に発音されます。
でも英語はどうでしたか?
音節の長さは一定ではありません。
複数の音節でできている単語では、アクセントがつく音節は1つだけで、はっきりと強く長く発音する音節もあれば、あいまいに弱く短く発音される音節もあります。
それは単語単位でも同じことが言えましたね(内容語と機能語)。
日本語では、音(音節)が変わる度に音程が変わります。
初めから聞えなくてもいい音なんてありません。
ただ歌の上手い人たちは、日本語の歌でもこの“曖昧な音程”を多用しています。
自覚がない人が多いとは思いますが。
それもこれも呼吸の連続性によるものです。
呼吸が途切れずに変化し続ければ、ある音からある音へと変化する間にも自然に音が現れます。
音と音を結んだ線、その線の中に音程が存在するということです。
点の位置は確実に取りたい音程です。その点は拍の頭になくてはなりません。
点と点を結ぶのも、直線でカクカク結んでいくのではなく、複数の点を一筆で結ぶ感じです。
かなり先までが見通せていないと一筆で結ぶことはできず、点ごとに留まってしまうわけです。
~スポンサーリンク~

英語の数字で練習

理屈ばかり考えていても仕方ないので実践あるのみです!
では、英語の1から10までの数字を使って練習しましょう。
ここでは、“連続して途切れない呼吸”と“母音を拍の頭に合わせる”という2つの練習を同時に行います。

赤で書かれているのが母音の発音記号です。
“Seven”は2音節ありますが、数字は1音節として発音するのが一般的なので、これも他と同じように一語として発音してください。
母音の前にある子音(T/Th /F/S/N)は、拍のほんの少し前で発音し、ちょうど母音になるところが拍の頭になるように意識します。

カタカナ1語にはすでに母音が含まれています。
厳密にいえば、日本語でも母音は子音の後に聞こえるので、拍の頭で「ツー(トゥー)」と言った場合、「ツウ(トゥウ)」と少し遅れてしまうことになります。
また、“かな”を一つ言った時点で1音節終わってしまいます。
一音節に母音は一つです。
その一つを拍の頭に合わせればよいということです。
※“Eight”は母音が頭にありますから、“E”を拍の頭で発音してOKです。かなり早く発音した場合には自然と音が連結してしまいますが、“数字”としてはっきり言うならリンキングさせないほうがいいかもしれません。
詳しくはフォロー動画で!
久々に見たら下手だったので手本になるかは微妙ですが(;”∀”)
ひとまず練習の方法と意図を理解してください。
“One~Ten”はそれぞれ独立した単語を続けて発音しているので、通常の英文よりも難しいです。
どの単語にもアクセントを付けることになるので呼気量も必要です。
これに比べたら、アクセントを付けなくていい語やとても弱く発音していい語が含まれる文章の方が簡単に感じられてきます。
無駄な隙間をつくらないように!
その隙間に、本当は子音が入ったり、音が次の音へと変化する最中の音が鳴っていることに気付きましょう。
まとめ 動画付き
- 音程がつくと呼吸が途切れやすい人は長文を読む練習から
- 長文を読む時はセンテンスの最後の語から
- 単語数が増える毎に呼吸が引き延ばしていく
- 音程をつけた場合、拍の頭に母音を発音する
- 呼吸の連続性が保たれると発音が良くなり隙間も埋まる
>>>次に進む

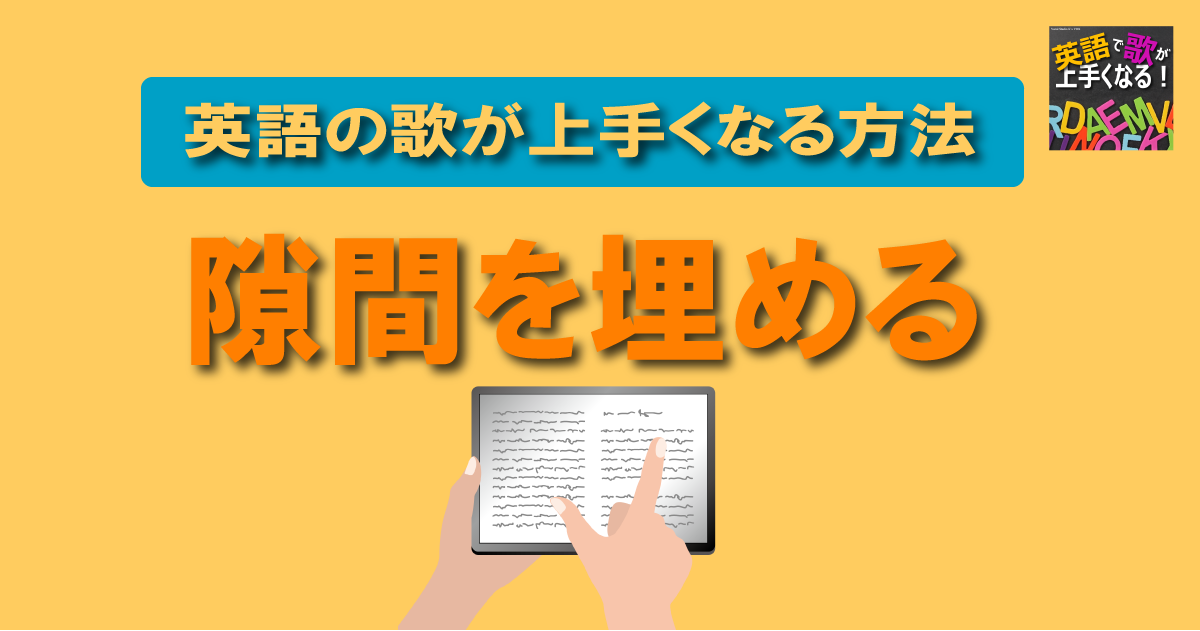
No responses yet