~目次~
想定内の失敗
英語の発音も歌も、一朝一夕に上達するものではありません。
変化、成長の過程には“副作用的現象”が現れます。
今回は、そのいくつかをお伝えしておこうと思います。
想定内の失敗なので、不安にならず確実に修正していきましょう。
- 息が足りなくなる
- テンポが崩れて拍を見失う
- 部分的に発音できなくなる
- 音程が外れる
- キーが分からなくなる
必ずと言っていいほど、このいずれかの現象が起きます。
-これじゃあ、歌が下手になってるじゃん
確かに一時的に下手になった気がすると思います。
ですが、広い意味では“変化”しているということです。
ここはどっしり構えて、原因を知り対策を講じましょう。
不慣れな英語でのデメリット

まだ完全には“英語らしい”発音にはなっていないからこそ、先ほど挙げたような失敗をしてしまいます。
“英語らしい”発音に近づくことで回避または改善していくので安心してください。
それでも原因が分からないと不安になるので、“なぜ失敗してしまうのか”について知っておきましょう。
英語でのメリットは、自分でコントロールできるようにならないと一転デメリットになってしまうことを理解しておけば、失敗も成長のプロセスと捉えることができ、その失敗を改善することでさらなる上達が見込めます。
【英語で歌うことのメリット】
- 腹式呼吸がマスターできる
- 日本語では使わない筋肉を鍛えられる
- 少し先を予期しながら呼吸の連続性を保つことができる
- ことばやメロディーに規則性を与えられる …など
【不慣れな英語でのデメリット】
- 無駄に息を吐き過ぎてしまう
- 閉じる動作が多い分、息を止めやすくなる
- アクセントがつかないと音程が欠けてしまう
- 有声子音にも音程をつけてしまう …など
“とにかく子音だけ強く鳴らしてみる”とか“息を止めずにただ流し続ける”といった、ある側面だけをクローズアップし過ぎると失敗を招きます。
複合的に、総合的に上達しない限り、英語のメリットは十分に発揮されません。
片足だけ、片手だけでは歩けないのと同じです。
片足だけを強く前に出しても歩くことはできません。
右足を出しながら左手を前に、体重を移動させながら次は左足を…なんてことも考えませんよね?
“あれをして、次にこれをして…ヽ(□ ̄ヽ))…((ノ ̄□)ノ”ではなく、すべてが連動しているのです。
失敗の原因と対策
息が足りなくなる原因

子音を強く鳴らそうとすればするほど息が足りなくなる。
これは初期によく起こる現象です。
とにかく息をたくさん吐こうとし過ぎています。
何度も説明したように、腹式の利点は呼吸がコントロールできることです。
やたらたくさん吐いて大きな声を出すことではありません。
短く速く吐くこともできれば、長くゆっくり吐くこともできます。
呼気量が少なくてもプツッと切れることがありません。
呼吸の連続性が保たれているので細かく緩急をつけることもできます。
それなのに、一辺倒に強く吐いてしまったら息が足りなくなって当然です。
子音を強く発音しようと、必要以上に息を吐くことはありません。
呼吸がしっかり流れているから、僅かな阻害でも音が鳴るのです。
低い音程であろうが、小さめの声であろうが、腹式呼吸でなら子音の音が調音されます。
強く大きな声にしないと子音の音が鳴らせないのなら、それは腹式呼吸ではないということです。
もっとあいまいに発音される音も短く弱く発音される音もあるのに、全部を強く発音しようとしていれば、それはもはや日本語になっています。
もともと声が小さく、呼気量も少なかったのであれば、一時的に息が足りなくなることはあります。
英語の発音をするために腹式呼吸の練習をしているのですから、一旦は“こんなに吐くの~?!”と苦しくはなるでしょう。
でも、いつまでも改善しなかったら問題です。
その発音は、本当に“英語らしい”発音になっていますか?
“内容語も機能語”も全部同じ強さになっていませんか?
吐くことばかり気にしていて、ちゃんと吸えていないのであればブレスも注意しましょう。
声を出すことで“呼気”にばかり意識を向けがちです。
腹式呼吸は“吸気”が大事です。
胸式で吸って腹式で吐くということはできません。
まずはしっかり深く息を吸えるようになることから!
息が十分に流れるようになってから、コントロールする練習をしましょう。
息を吐き過ぎるのとは逆に、息が吐けなくて息苦しい人もいるかと思います。
それは阻害が強すぎるせいです。
阻害させるだけで阻害音を鳴らせていなければ、息を止めてしまったことになります。
この場合はアクセントも付きません。
母音で息が減衰しているか、母音を“かな”で言い直していると思います。
小さい声から大きな声、低い音程から高い音程まで、同じ発音ができるように練習してみてください。
声の大きさや高さで発音が変わらないようにしましょう。
音程が外れる(甘くなる)原因

発音を気にして歌ったら、音程が甘くなってしまった。
少し英語に慣れてきた頃に起こる現象です。
子音の音や呼吸の流れを気にして歌ったことで、随分“英語っぽく”聞えはするのですが、よく聞くと音程が?!
これも、まだ“英語っぽい”だけで“英語らしく”はなっていないことが原因です。
息が流れることで自然に子音が調音されるようになり、子音骨格での発音になれば英語の音節になります。
正しい英語の音節で発音されていればアクセントがつきます。
でも、どこかまだ不十分であるがゆえにアクセントがつかず、音程が欠けてしまうのです。
はっきり音程がついているのは“アクセントのついた母音”だけでしたね。
その母音が上手く鳴らなければ、音程もまた上手く取れません。
アクセントがつかなかったことで、あいまいな音になり、あいまいな音程になります。
カタカナ英語でたくさんの母音をつけてしまい、不必要な音程を加えていた人はとくに注意です。
カタカナをやめようとした結果、今度は全部の母音を曖昧に発音しようとしてしまうことがあります。
✖英語っぽい発音→アクセントがつかない→音程が外れる
✖音程をしっかり取る→カタカナが増える→日本語っぽい発音
〇英語らしい発音→アクセントがつく→正しい音程が取れる
一進一退を繰り返しながら上達するしかありません(;^ω^)
アクセントのついた母音が音符になるので、その母音があいまいになってしまうと拍も見えづらくなります。
そのせいでテンポも取りにくくなります。
まだ英語の発音に慣れていない人は、良くも悪くも呼吸が速くなるので、全体的に走ってしまう(テンポが速くなってしまう)と思います。
そこに甘い音程が加わることで、いっそうテンポが乱れやすくなります。
休符を意識したり、音符の長短を気にして、出来るだけリズムとしてのまとまりを歌うようにしてください。
各フレーズの1~2か所をどこかで合わせるようにすると良いでしょう。
“ちょうど3拍目に、この長母音を合わせる”
“2拍目の頭にこの単語のアクセントがくる”など。
1語ずつ、1音ずつ合わせようとしてしまうと呼吸がつながらなくなって、ますます子音もアクセントも消えてしまいます。
合わせるポイントは最小限にしたほうが良いです。
~スポンサーリンク~

キー(調性)やスケール(音階)が分からなくなる原因

それぞれの曲には“Cのメジャースケール”や“Aのマイナーペンタトニックスケール”などキーとスケールがあります。
キーとスケールについての説明は割愛しますので、興味のある人は他のサイトを参照してください。
音楽には規則性があり、規則性とはある種の秩序です。
秩序のない音の羅列は予期することができません。
次にどんな音がくるか想像もつかない曲では覚えることもできません。
わたしたちは、無意識的にその曲のキーとスケールを感じ取っています。
音楽理論なんて知らなくても、あからさまに音程を外されれば気が付きます。
それは秩序が乱れたと感じるからです。
適度にあいまいな音程がある分には問題ありません。
なぜなら、所要な音程にちゃんと秩序があるからです。
でも、主要な音程があいまいになっていたらどうでしょう?
さらにあいまいな音程の方が強く聞えていたら?
聴き手以前に歌っている本人が自分の歌で混乱してしまいます。
その場合は、一度主要なラインを“ラララで歌う”などして確認してみましょう。スケール上の正しい音程と音程らしきものを区別できるように!
一進一退の攻防はまだまだ続きます(;^ω^)
確かな一歩を大切に、諦めず英語も歌も上手くなりましょう!
まとめ
- “英語らしさ”を獲得する過程での失敗は想定内
- 失敗も成長のプロセス!
- なぜ失敗したのか、その原因を分析することが大切
- どの失敗も一時的な現象で、英語の発音が良くなれば必ず改善する
いくら失敗やミスをしても構いません。
ですが、それに気付けないと困ります。
自分で録音・録画したり、第三者に聞いてもらうなどして、現状を把握しておくように努めましょう。
きれいごとに聞こえるでしょうが、失敗をしたからこそ得られることがあります。
弱点だったところが、人よりも注意深く、また努力を重ねたことで、気付けば“強味”に変わっていることがあります。
決して失敗を恐れないでください。
>>>次に進む

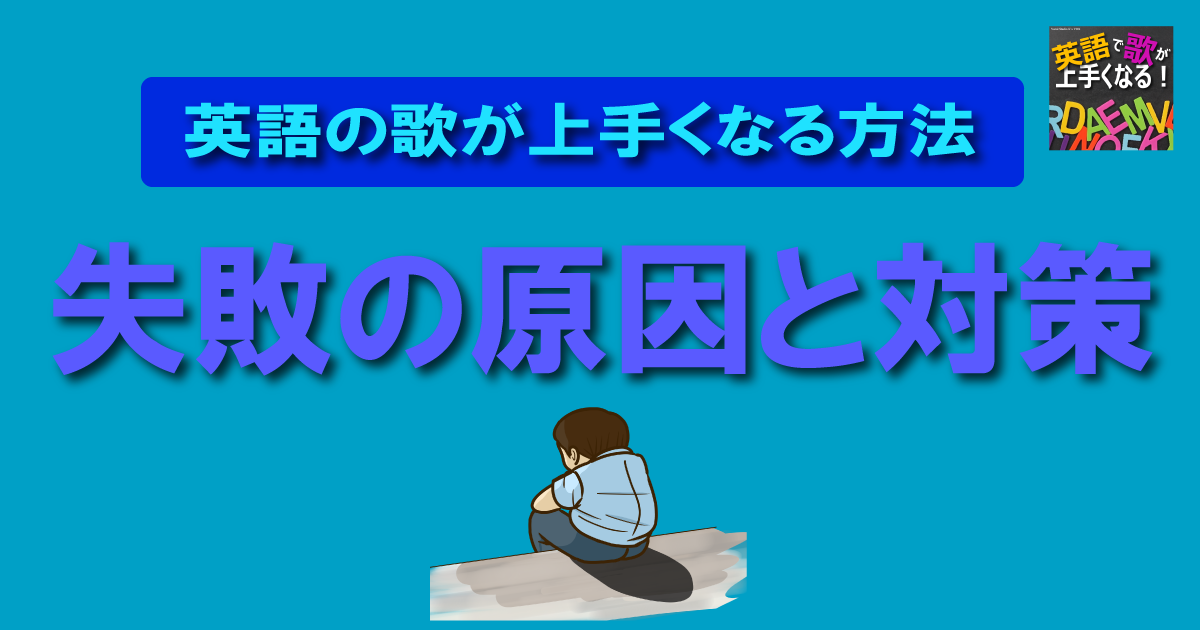
No responses yet